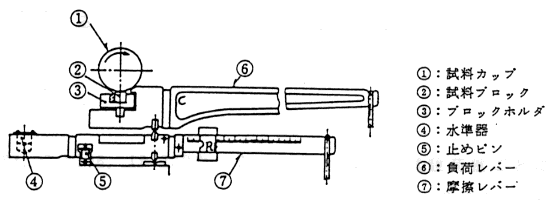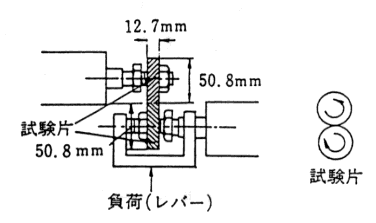|
ID-180 極圧試験の評価方法 潤滑剤に要求される各種性能の中で、極圧性は重要な性能の一つであり、各種機械の運転条件が過酷になるにつれ、潤滑剤の極圧性向上が要求されます。極圧性は耐荷重能ともいわれ、摩擦面の接触圧力が高く、潤滑する油膜の破断が生ずるような極圧潤滑下で潤滑剤が摩擦面の焼付きや融着などの損傷を防止する性能をいいます。極圧性試験(耐荷重能試験)の代表的なものには、四球法、チムケン法、SAE法、ファレックス法などがあります。 |
表1 耐荷重能試験機
| 試験機名称 | 曽田式四球試験機 | シェル式 四球試験機 |
チムケン 試験機 |
SAE 試験機 |
アルメン 試験機 |
ファレックス 試験機 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準法 | JIS法 | ||||||
| 試験片形状 |  |
 |
 |
 |
 |
||
| 接触様式 | 点接触 | 点接触 | 線接触 | 線接触 | 面接触 | 線接触 | |
| 運動の種類 | すべり | すべり | すべり | すべりと ころがり |
すべり | すべり | |
| 回転速度, rpm | 200 | 750 | 1500 | 800 | 1000 | 600 | 290 |
| 速度, cm/s | 11.4 | 42.8 | 56 | 200 | 232 | 20 | 9.8 |
| 負荷方法 | 油圧 1分ごと に増加 |
油圧 各荷重で 1分 |
てこ荷重 各荷重で 10〜60秒 |
てこ荷重 各荷重で 10分 |
てこ荷重 各荷重で 1分 |
てこ荷重 と油圧 |
油圧 各荷重で 3〜10分 |
| 給油方法 | 浸せき | 浸せき | 浸せき | 循環 | スプレー | 浸せき | 浸せき |
|
1.四球試験 日本で開発された曽田式と、欧米で広く用いられてきたシェル式が良く知られています。いずれも試料容器底に、水平に固定された3個の固定球の中心上に回転球を押し付け、接触する3点を摩擦部とします。 | |
| a) | 曽田式四球試験 標準法(ステップ法)とJIS法(JIS K 2519、ショック法)があります。 標準法は回転数200rpmで、毎分規定の負荷油圧を焼付きを起こすまで上昇させ合格限界を求めます。 JIS法は回転数750rpmで荷重を加えたあと1分間回転させます。毎回、試験球と試料油を換え、焼付きが発生するまで規定の負荷を上昇し、この操作を繰り返して合格限界荷重を求めます。 |
| b) | シェル四球試験 試験法には、ASTM D 2783,D 2596(アメリカ材料試験協会),IP 239(イギリス石油協会)などがあり、いずれも試験荷重ごとに試験球、試料油を換え荷重を加えたあとにショック的に回転させます。荷重段階、回転時間、回転速度は試験法によって異なります。IP 239には、初期焼付き荷重、融着荷重、平均ヘルツ荷重などの測定方法があり、ASTMでは融着荷重や荷重−摩耗指数の測定を規定しています。 |
|
2.チムケン試験 | |
試験法には、JIS K 2519,ASTM D 2782,IP 240などがあります。図1に示すように試験カップ(リング)(1)が回転軸に取り付けられ800rpmで回転し、下部ホルダ(3)に固定された試験ブロック(2)と線接触します。負荷レバーによって荷重を加え、10分間摩擦によって焼付きを生じない最大荷重をもとめます。 | |
|
図1 チムケン試験機の試験部
| |
|
3.SAE試験 | |
試験法はFed. Test Method Std.791-6501.1(アメリカ連邦規格)に規定されています。ギヤー油の極圧性の判定のために設計されたもので、図2のように、2個の鋼製リングをころがり−すべり接触させ、レバーで荷重を加えて焼付き限界を判定します。2個のリングとも回転するため、接触形状に大きな変化がないという長所があります。 |
図2 SAE試験機
|
|
4.ファレックス試験 試験法は、ASTM D 3233(極圧性),D 2670(摩耗),IP 241があります。回転する垂直軸の試験ジャーナル(ピン)を両側より2個のV字ブロックで圧し、試料油中で摩擦します。極圧性評価法の ASTM D 3233 には、レバー荷重を連続的に上昇させて焼付き限界を求めるA法と、段階的に負荷上昇させるB法があります。 | |
| [参考文献] 日本潤滑学会編:潤滑ハンドブック(改訂版),養賢堂(1987) |
|