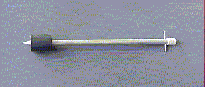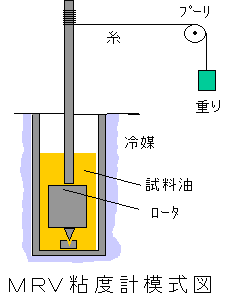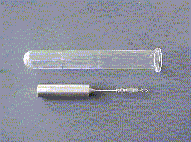1.潤滑油の低温粘度
潤滑油の主成分である基油は、液体の特性として温度が下がるとともに粘度が高くなります。基油として最も普通に使われている鉱油にはワックス分が含まれており、低温条件ではワックス分が析出しゲル状の構造を作ります。このため、低温下では常温〜高温領域での単純な粘度-温度特性とは異なった粘度特性(見掛け上高い粘度)を示すようになります。また、このゲル状構造は壊れ易いために機械的な作用で粘度が変化します。そこで、潤滑油の用途に応じて、種々の条件下で低温見かけ粘度を測定する必要があります。このように、せん断速度によって見かけ上の粘度が変わる液体は非ニュートン流体と呼ばれます。
現在広く採用されている低温粘度の測定装置には次のようなものがあります。いずれも回転粘度計の一種です。
・CCS粘度計(エンジン油)
・MRV粘度計(エンジン油)
・スキャニングブルックフィールド粘度計(エンジン油)
・ブルックフィールド粘度計(自動車用ギヤ油、ATF、油圧作動油等)
なお、潤滑油が低温により流動性を失う温度(流動点)とこれら各種の低温粘度とは直接の相関はありません。
2.各種粘度計について
-
(1)CCS粘度
-
エンジン始動時にはセルモータでエンジンクランク軸を回転させますが、低温下でエンジン油が固くなっているとクランキングが重くなり、エンジンが始動できなくなります。そこでクランキングをシミュレートした粘度計(CCS粘度計、Cold Cranking Simulator)でCCS粘度を測定し、エンジン油の低温始動性の評価を行ないます。この粘度はSAE J300の中に低温粘度の規格の一部として定められています。
試験法はASTM D 5293(Standard Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils Between -5 and -30℃ Using the Cold-Crankig Simulator)、JIS K2010(自動車エンジン油粘度分類 付属書A コールド・クランキング・シミュレータを用いた−40℃から0℃のエンジン油の見掛け粘度試験方法)に規定され、エンジン油の粘度規格SAE J300に用いられています。(ASTM D 2602でもASTM D 5293と同様の試験装置を用いますが測定温度が-28.9℃、−18(−17.8)℃でした。これは実際のエンジンとの相関が低かったため、ASTM D 5293に置き換わりました)。
写真1は、自動CCS粘度計の内部写真です。中央の黒い部分にロータとステータがセットされています。ロータとステータを取り出した状態が写真2および写真3です。
CCS粘度計は、せん断速度が104〜105/sという高速回転条件で0〜−40℃における500〜200、000mPa・sの粘度を測定できます。まず、試料油をロータとステータの間に満たし、規定温度まで急冷します。規定温度に達したらロータを規定トルクで回転させ、速度指示計の読みを記録します。あらかじめ粘度が既知の標準油で検量線を作成しておき、グラフから粘度を読み取ります。最近はコンピュータによる全自動計測が可能になっています。
-
(2)MRV粘度
-
低温下ではオイルパンの中のエンジン油は流動性を失い、オイルポンプはエンジン油を吸入できなくなってしまいます。この現象は二つの原因によって起こります。ひとつはエアバインディングといって、エンジン油を空気と共に吸入してしまうこと、もう一つはフローリミテッドキャビテーションといって吸入管内の流動性が失われるためにエンジン油を吸い込めなくなりキャビテーションを起こすことです。これらはいずれもエンジン損傷(ベアリング摩耗等)の原因となります。これらの現象と相関のある粘度を測定する装置がMRV粘度計(Mini Rotary Viscometer)です。この粘度はSAE J300の低温粘度の規格値として採用されています。
試験法はASTM D 4684(Standard Test Method for Determination of Yied Stress and Apparent Viscosity of Engine Oils at Low Temperature)に規定されて、これがSAE J300に採用されています。同様の試験機を用いる試験法にASTM D 3829(Standard Test Method for Predicting the Borderline Pumping Temperature of Engine Oil)があります。両者の違いは冷却速度にあり、ASTM D 4684ではTP−1サイクルと呼ばれる、ASTM D 3829よりもゆっくりとした速度で冷却されます。TP−1サイクルが考案された理由は、実際のエンジンでの現象とより相関性が高いためです。MRV粘度計では、上述したCCS粘度計よりもはるかに低い冷却速度・せん断速度となっています。MRV試験機では、冷却によって生成したワックス分によるゲル構造を壊さないようにせん断速度が1〜50/sという低い速度で測定が行なわれます。
規定量のサンプル油をセル内(ステータ)(内径19mm)に入れ、ロータ(外径17mm、長さ20mm写真4)を差し込んだ後にロータ軸(直径3.18mm)に糸を巻き付けます。
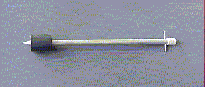
写真4
|

写真5
|
サンプル油を80℃まで上昇させた後、ASTM D 4684ではTP−1冷却サイクルというプログラムされた冷却速度で、ASTM D 3829では測定温度まで10時間かけて冷却し、その後温度を保ったまま16時間後に測定を開始します。
まず、ローターシャフトの糸をプーリーにかけ、重り(10gづつ)をつるしてシャフトが回転する荷重を測定します図1。
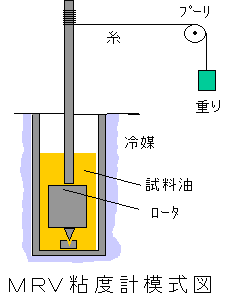
図1
|
これをイールド・ストレス(Yield Stress - 降伏応力)と言います。次におもりを150gに変え、目視で回転数を数えます。回転数から計算式によって粘度を算出します。
イールド・ストレスはエアバインディングと、粘度はフローリミテッドキャビテーションと相関があるとされています。
-
(3)スキャニングブルックフィールド粘度
-
ある種のエンジン油では市場においてゲル状化してエアバインディングをおこす事例が見つかりましたが、この現象は従来のMRV粘度計では評価できないことがわかりました。そこで新たな試験法が開発され、ASTM D5133(Standard Test Method for Low Temperature, Low Shear Rate, Viscosity/Temperature Dependence of Lubricating Oils using a Temperature-Scanning Technique)として規定されました。この粘度の規格はAPI−SJ(ILSAC GF2)から採用されています。
MRV法のせん断速度はせん断応力525Pa時に100/sですが、スキャニングブルックフィールド法ではせん断速度が1.7/s、せん断応力は最大70Paと、MRV法に比較して小さな値となっています。
粘度計はブルックフィールド粘度計を用いますが、スキャニングブルック粘度計には特に設計されたステータ・ロータが使用されます。ステータは長さ140mm、直径22.05mmのガラス製試験管で、ロータは長さ65.5mm、直径18.4mmとなっています写真6。試料油(20ml)をセル(ステータ)に入れ、ロータを挿入して冷媒に浸漬します。冷媒を1℃/hの冷却速度で冷却しつつ、ロータを先程のせん断速度(0.3rpm)で回転させ、トルクを連続的に記録していきます(トルクから粘度が求められます)。試験は−40℃もしくは粘度が40000mPa・sに達するまで行ないます。ゲル化するオイルではある温度から急激に粘度が上昇を示します。温度変化に対する粘度変化量からゲレーション・インデックスを求めます。具体的には、温度1℃毎に次式にしたがってX、Yから、-1×(X/Y)を求め、全測定温度範囲中のもっとも大きな-1×(X/Y)の値をゲレーション・インデックスとします。
X : 試験温度1℃毎のLogKの差 (Kは絶対温度)
Y : 試験温度1℃毎のLogLog(η)の差 (ηは粘度、mPa・s)
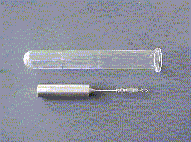
写真6
|

写真7
|

写真8
|
写真7は粘度計を作業台に乗せてロータをセットした様子、写真8は冷却槽にセットされた様子です。
ILSAC GF−2規格では、ゲレーション・インデックスを12以下に規定しています。
-
(4)ブルックフィールド粘度
-
自動車用ギヤ油、ATFおよび油圧作動油等の低せん断速度での低温粘度を測定するために使用されます。試験法はASTM D 2983(Standard Test Method for Low-Temperature Viscosity of Automotive Fluid Lubricants Measured by Brookfield Viscometer)に規定されています。粘度の測定範囲は1000〜100万mPa・sで、温度範囲は−5〜−40℃となっています。
ブルックフィールド粘度計にはいくつかの太さのスピンドル(ロータ)が用意されていますが、この試験法では#4を使用することになっています。セル(ステータに相当する)は直径22mm、長さ115mmの試験管です。このスピンドルとセルの組み合わせでは、せん断応力およびせん断速度は次の式で求められます。
T(せん断応力、Pa)=1.253×M(粘度計の読み)
S(せん断速度、/s)=0.2156×rpm
約30mlの試験油をセルに入れ、50℃で30分間加温した後、30分間室温に放置し、次に測定温度に保った空気浴中に15.5時間放置します。予想される粘度によってロータの回転数は決められており(0.6rpm@100万mPa・s最大から60rpm@1000mPa・s最小まで7段階)、予め粘度計の回転数を設定しておきます。空気浴から手早くセルを取り出し、スピンドルをセットした粘度計を取り付け、測定温度に保った液体浴に移し替えて30分後に測定を行ないます。粘度計の設定回転数でスピンドルを回転させ、その時の粘度計の読み(100度目盛り)を記録します。各回転数ごとに係数が決めらているので、粘度計の読みに係数をかけることによって粘度を求めることができます。空気浴から16時間後に取り出した後、セルを断熱容器に移して測定する方法でも良いのですが、この方法では測定時の温度変化が避けられないのであまり好まれないようです。
|