| ID-233 赤外分光法の潤滑管理への応用について |
|
赤外吸収スペクトルの測定により潤滑油剤の劣化、汚染管理を行うことがあります。以下に赤外分光法の概要、潤滑管理への応用例および留意点などを簡単に説明します。 赤外光が物質を透過する際に吸収される現象を赤外吸収といいます。分子は全て化学結合した原子から作られていますが、これらの化学結合と原子はバネと玉から作られた系に似た運動をしており、絶えず伸びたり縮んだり(伸縮振動)あるいは角度が変わったり(変角振動)しています(図1)。 |
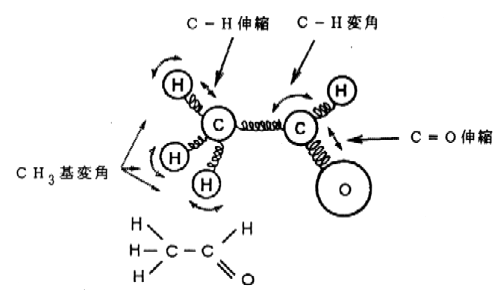
図1 アセトアルデヒドの伸縮,変角振動
| このような構造をもった分子にある振動数(振動数は波数に光速度をかけたもので単位はサイクル/sec)を持った赤外光があたった場合に、それと同じ振動数で振動しているバネが分子中に存在すればバネは赤外光を吸収し、そのエネルギーでバネの振動は一層激しくなりますが、通過した赤外光の強さは弱くなります。もし該当するバネがないと赤外光は吸収されずにそのまま分子を通過します。つまりこの現象を利用して試料に赤外光(波長2.5〜25μm−波数4000〜400cm−1)を照射し、吸収のスペクトルを測定したものが赤外吸収スペクトル(Infrared Spectrum:IR)といい、これによって物質の定性、定量を行う手法を赤外分光法といいます。 現在では各種の化学結合(官能基)についての吸収位置が明らかにされており、多くの物質についてのスペクトルデータが文献等に公表され、データベース化も行われています。 |
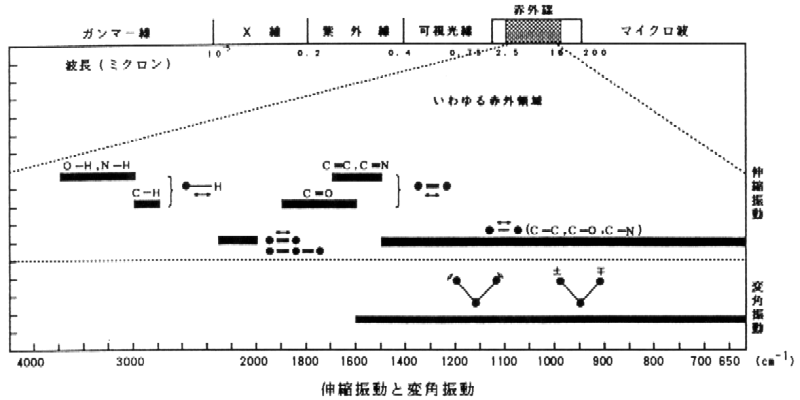
図2 化学結合と特性吸収
| 赤外吸収スペクトルでわかることは以下の3点に大別されます。 | |
|
(1)物質の同定 既知の赤外吸収スペクトルとの比較により同定、確認 |
|
|
(2)未知物質の構造の特徴 化学結合や官能基から構造の推定 |
|
|
(3)定量分析 混合物の成分比、純度の測定等 |
|
| 以下に測定方法と分析技術をまとめてみました。 |
|
| 1).試料調製法 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2).差スペクトル 3).特性吸収帯 潤滑管理への応用については以下のようなことが挙げられます。 |
|
| (1) | 潤滑油剤の劣化、汚染管理 赤外吸収スペクトル法を利用したルーチン・モニタリングによって、潤滑油剤の化学的組成の変化を追跡します。潤滑油剤の劣化、汚染管理にその効果が期待できます。 また、使用中の潤滑剤の赤外吸収スペクトルを新油のそれと比較することにより、使用期間中における潤滑油及び機械装置システム等の性能に関する変化を知ることができます。 |
| 例 |
1).潤滑油剤の酸化劣化 2).潤滑油添加剤の消耗度の判定 3).各種コンタミの分析 ・水分の混入 ・異種潤滑剤の混入 ・外部環境からの物質の混入 |
| (2) | 潤滑トラブル等の分析 各種の分析機器のうちで赤外吸収スペクトル装置は最も汎用的に利用されています。特にフーリエ変換型装置の登場によって性能が飛躍的に向上し、μgレベルの微量サンプルへも適用範囲が広がりました。 |
|
応用例 1).摩擦摩耗表面の分析 2).潤滑トラブル原因解明への応用等 |
|
|
以下に、その具体例を示しました。 1). 潤滑油剤の酸化劣化 |
|
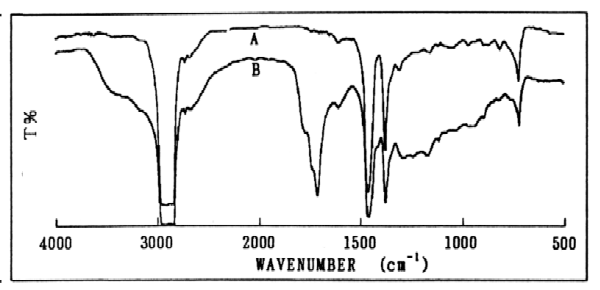 A:新油 B:4.5年使用後 図3 酸化によるギヤー油の経年変化
|
|
2) 各種コンタミの分析 ・水分の混入 |
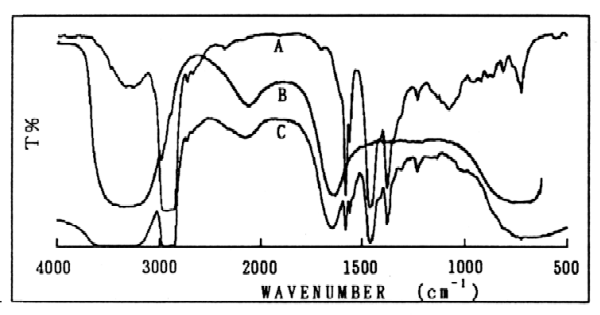 A:未使用品 B:水 C:使用後グリース 下水処理場の水処理装置で48時間使用したベアリングより採取したもの 図4 グリースへの水分混入
|
| ・異種潤滑剤の混入 |
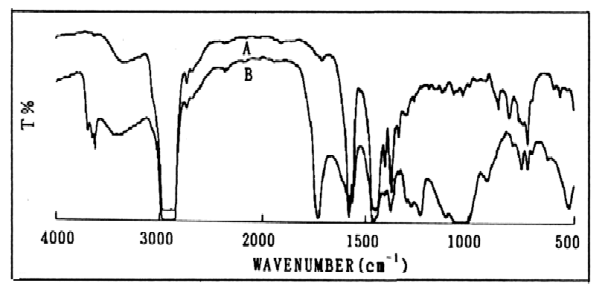 A:未使用品 B:使用後グリース 運転1200時間後潤滑不良を起こしたピローブロックベアリングから採取したもの 図5 リチウムコンプレックスグリースへの異種潤滑剤の混入
|
|
赤外吸収スペクトル法は極めて役に立つ技術ではありますが、分析手段として単独で用いるのは好ましくありません。例えばコンタミによる潤滑トラブルが発生した場合に赤外吸収スペクトルだけから原因物質を同定するのはかなり難しいと考えられます。それを容易にするかどうかはそのトラブルに関してどの程度の情報が得られたかにかかっています。 つまりできるだけ多くの周辺データや情報を収集した上で、赤外吸収スペクトルを利用することが有利であり、それが問題解決への鍵となります。 |
| [参考文献] 日本分光,FT−IR分析法テキスト 日本分光、IR分析の原理と基礎知識 吉元直弘、三菱石油技術資料、73.24〜36(1989) JaniceR.Addiis, NLGI Sporkesman,54,1,16〜21(1990) |
|
Copyright 1999-2003 Japan Lubricating Oil Society. All Rights Reserved.