|
ID-S33 すべり軸受はどのように負荷を支えるか エンジン軸受は、なぜ大きな負荷を支えることができるのでしょうか。 すべり軸受、平軸受と呼ばれている軸受を代表するものとして、自動車のエンジン軸受が挙げられます。エンジン軸受とは図1に示す、クランクシャフトを支える半割のメインベアリング、コネクティングロッドベアリング(以下コンロッドベアリングと略す)とクランクシャフトのスラスト力を支えるクランクワッシャなどをいいます1)。 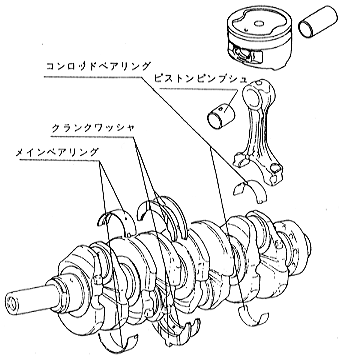 図1 エンジン軸受の使用箇所 燃焼等により得られたピストンの上下運動を、クランクシャフトで回転運動にかえるレシプロエンジンの構造は、エンジン軸受に複雑な荷重を加えます。その荷重の発生する機構を、図2に示しました。  図2 エンジン軸受にかかる荷重の形態 エンジン軸受にかかる荷重は、爆発荷重、回転慣性荷重、往復慣性荷重の3種類に大別されます。これらの荷重はクランク軸の回転に伴って複雑に組み合わさり、その大きさと方向が刻々と変化します。その変化の様子は図3に示す荷重極線図で表され、この例のコンロッドベアリングの場合は最大約20kNもの荷重が軸受にかかります。  図3 荷重極線図 この荷重を軸受の投影面積で除した値が面圧です。図4はコンロッドベアリングにおける面圧と軸周速との関係を、各種のエンジンごとに調査しプロットしたものです。エンジンの種類により負荷の形態はかなり異なるが、コンロッドベアリングは約20〜60MPaの面圧を受けながら、約5〜20m/sの高速で回転するシャフトを支えていることになります。  図4 コンロッドベアリングにかかる負荷の大きさ エンジン軸受がこうした大きな負荷を支えることを可能にしているのが流体潤滑です。流体潤滑における油膜圧力発生の原理は図5に示す単純なモデルで表されます。すべり面の間に潤滑油のような粘性流体をはさみ相対運動すると、潤滑油はすべり面に引きずられて流体膜の中で速度分布が発生します。このとき図5−aのように先細りのすきまの場合には、流体は押し合いへし合いして圧力が発生します。これをくさび膜圧力と呼びます。また面をすべらすかわりに、図5−bのようにこのすきまを押しつぶすと、間にはさまった流体は両側へ押し出されます。ところが粘性はその流れの邪魔をするために圧力が発生することになります。これを絞り膜圧力と呼びます。  図5 流体潤滑の原理 油膜圧力発生の原理は、大きくはこのくさび膜圧力と絞り膜圧力の2つの作用によるものです。これらの作用によって発生する油膜圧力の大きさは、約100年ほど前にOsborne Reynoldsによって導かれた、いわゆるレイノルズ方程式により計算されます2)。 このレイノルズ方程式を用いて計算した一定荷重下における円筒形軸受の油膜圧力分布を図6に示します。 この例では最大約250MPaの油膜圧力が発生しています。エンジン軸受はこのような大きな油膜圧力によって大きな負荷を支えており、理論上は軸と軸受とは直接に接することはありません。  図6 円筒形軸受における油膜圧力分布 前述したように実際のエンジン軸受の荷重は複雑に変動するため、油膜圧力分布の形と大きさは常に一定ではなく、時間とともに刻々と変化します。この変化の状況を正確に知るためには、軸の中心の動きをとらえる必要があります。この軸心の動きは軸心軌跡と呼ばれ、クランク角の各時刻における荷重とレイノルズ方程式から計算した油膜圧力とのつり合いより求められます3)4)。 この軸心軌跡から、エンジンの1サイクル中の最小の油膜厚さとその位置がわかります。直列4気筒1999-2003ccのガソリンエンジンのコンロッドベアリングにおける軸心軌跡図を図7に示しました。  図7 軸心軌跡図 この場合直径約60mmの軸と軸受を隔てる最小油膜厚さは約0.6μmとなります。この厚さを直径100mの日本一の大観覧車を軸に見立てて比較したものが図8です。  図8 油膜厚さの概念 直径100mの軸を支える軸受があったとすると、その時の最小油膜厚さは実に1mmとなり、蟻が通れるかどうかという隙間です。大きな負荷を支える油膜の厚さは、実は非常に薄いものです。こうした理想的な潤滑状態である流体潤滑を維持するためには、軸と軸受の加工精度、表面粗さ、軸受材料と潤滑油の選定などが重要となります。 エンジンの高性能化による現代の自動車が獲得したスピードは流体潤滑の賜であり、エンジン軸受が潤滑油とともにそれを支えたと言っても過言ではありません。 |
|
「参考文献」 1)大豊工業株式会社デザインガイド(1992) 2)Osborne Reynolds:Philosophical Transactions, 177 (1886) 157. 3)木村好次・岡部平八郎:トライボロジー概論(1982)98. 4)Shozo Sasaki et al.:SAE Technical Paper 870581 (1987). |
|
「出典」 |
Copyright 1999-2003 Japan Lubricating Oil Society. All Rights Reserved.