| ID-354 環境ホルモンについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「環境ホルモン」という名称は、そもそも日本で主に使われている名前です。 正式な名称は「外因性内分泌かく乱化学物質」。身体の外にある物質が原因で、ホルモンすなはち内分泌が、かく乱するという意味です。 海外では、 「Endocrine Disruptors」 (エンドクリン・ディスラプターズ=内分泌かく乱物質) 「Endocrine Disrupting Chemicals」 (エンドクリン・ディスラプティング・ケミカルズ=内分泌かく乱化学物質) と呼ぶのが一般的です。 そもそも環境ホルモンとは、一つの化学物質をさしてるわけではありません。 これは、ホルモンの働きをかく乱すると言われる化学物質の総称です。 これらの化学物質には、さまざま定義がなされています。 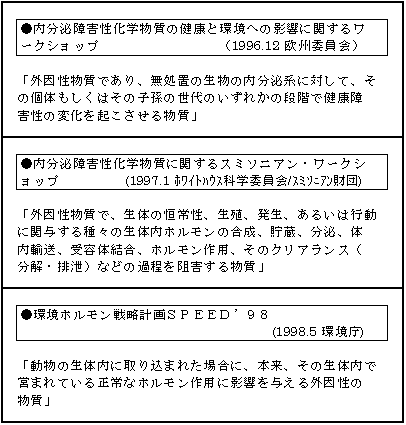 「環境ホルモン」をめぐる一連の流れ(化学物質をめぐる動き・規制への動き・化学物質の汚染の状況)を下記に示します。
上記の通り、環境ホルモンの定義は依然あいまいである。そして定義それ自体が確定していないため、環境ホルモン物質の種類もはっきりしていません。 環境庁の研究班での中間報告(1999-2003年7月)では、67種類 「奪われし未来」では、63種類 (社)日本化学工業会では、海外の諸文献から144種類の化学物質が環境ホルモンと疑われる物質としてリストアップされている。 【総合すると現在、環境ホルモンとして疑われている物質は約70〜150種類あると考えられる。】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 化 学 物 質 | |
|---|---|---|
| 産業化学物質 | ・合成洗剤・染料・化粧品 ・プラスチック・可塑剤 など |
・ノニルフェノール・オクチルフェノール ・ビスフェノールA・フタル酸ブチルベンシ ・フタル酸ブチルベンジル など |
| ダイオキシン | ・ゴミ焼却 ・金属精錬 ・紙の漂白 など |
・ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン ・ポリ塩化ジベンゾフラン ・コプラナーPCB |
| 農 薬 | ・除草剤 ・抗真菌剤 ・殺虫剤 など |
・DDT・DDE・DDD・エンドスルファン ・メトキシクロル・ヘプタクロル・トキサフェン ・ディルドリン・リンデン など |
| 天然物質 | ・クローバー・ニンジン ・大豆 ・じゃがいも など |
・フォルモノネティン ・クメストロール など |
| 医薬品 | ・流産防止薬 | ・DES ・エチニルエストラジオール(ピル) など |
| 主 な 用 途 | 物質数 | 主 な 規 制 な ど | |
|---|---|---|---|
| 農薬 | 殺虫剤 | 22 | 毒劇法、食品衛生法、化審法、POPs、 土壌残留性農薬、家庭用品法、 水濁性農薬 |
| 殺ダニ剤 | 1 | 食品衛生法 | |
| 除草剤 | 7 | 毒劇法、食品衛生法、海防法、水濁法、 水道法、地下水・土壌・水質環境基準、 水濁性農薬 | |
| 工業製品: | |||
| 電機製品 | 1 | 地下水・土壌・水質環境基準、POPs | |
| ノンカーボン紙 | 1 | 化審法、生産中止、水濁法、海防法、 廃掃法 | |
| 難燃剤 | 1 | ||
| 殺菌剤 | 9 | 化審法、POPs | |
| 有機合成原料 | 1 | ||
| 防腐剤・漁網防腐剤 | 1 | 毒劇法、水質汚濁性農薬 | |
| 分散染料 | 1 | ||
| 樹脂の硬化剤 | 1 | 食品衛生法 | |
| 船底塗料 | 2 | 化審法、家庭用品法 | |
| 界面活性剤の原料 | 2 | 海防法 | |
| 分解生成物 | 2 | 海防法 | |
| 樹脂原料 | 1 | 食品衛生法 | |
| プラスチック可塑剤 | 5 | 水質関係要監視項目、海防法 | |
| 染料中間体 | 1 | 海防法 | |
| 医療品合成原料・保香剤 | 1 | ||
| スチレン樹脂の未反応物 | 1 | 海防法、毒劇法、悪臭防止法 | |
| 非意図的生成物/重金属 | 1 | 大防法、廃掃法、POPs | |
|
出典:(株)環境総合研究所 |
|
・化審法:化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律 ・大防法:大気汚染防止法 ・水濁法:水質汚濁防止法 ・廃掃法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・POPs:陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画に指定された残留性有機汚染物質 ・土壌残留性農薬等:農薬取締法 ・家庭用品法:有害物質を含有する家庭用品の規制法律 |
| 実態調査 | 環境モニタリングの充実 | 調査対象の化学物質数、調査地点の充実 調査する生物数の拡大 鳥類やほ乳類などの野生生物の影響調査 |
| 人の健康影響調査 | 環境ホルモンと関係が指摘されている疾患についての疫学的調査 精液性状に関する経年的なモニタリング調査 |
|
| 研究解明 | 生殖・神経・免疫等の影響に関する動物実験 レセプター等を介した作用メカニズムの解明 毒性の決定時期を特定するための研究 バイオマーカーの研究 スクリーニング手法を含めた試験法の開発 体内動態に関する研究 予防法に関する研究 動物の種差を利用した比較内分泌学的研究 リスク評価 |
|
| 研究情報 | 国内外にわたる研究情報交換の仕組みが必要であり、具体的には、 ・研究者間の連携のためのワークショップの開催 ・国際的、学術的な共同研究の推進など |
|
Copyright 1999-2003 Japan Lubricating Oil Society. All Rights Reserved.