| ID-S11 滑り軸受の限界について |
|
すべり軸受の限界について 限界の使用条件を述べる前にまず、すべり軸受の限界とはどのような損傷を被った時の事を言うのかという点から考えてみたいと思います。 軸受とは言うまでもなく、回転などの運動をする軸を受けるもので、その軸の運動が円滑に行われるという役割をになっています。その点から、軸の動きを停止させるような軸受の焼付きの損傷は致命的で、焼付き限界をすべり軸受の限界ととらえるのが自然でしょう。その他、振動、異音の発生やシール部の油漏れの原因となる軸受の異常摩耗などもある意味での限界ととらえられます。 ではまず、乾燥摩擦、境界潤滑でのすべり軸受の限界条件はどのようなものかについてみてみます。 すべり軸受の使用にあたり、その焼付き限界を表現する指標としてPV値という値がよく使われます。それは、軸受が受ける面圧Pとすべり速度Vが焼付きの主要な要因となる事が多い、という経験からきています。現実に、給油の全くない乾燥での摩擦、および油があっても非常にわずかである境界潤滑の場合には、図11)の破線で示すように軸受の焼付き限界はPV値で支配されることが多いです。当然、その他に摩擦面の表面性状、吸着膜なども限界に影響を及ぼします。また、これらを詳しく調べていくと摩擦面の表面温度に依存する場合がほとんどであることがわかります。 |
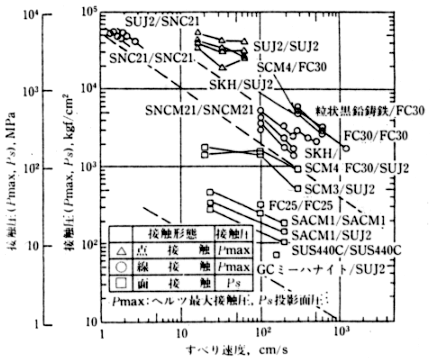
図1 点・線・面接触形態のPV限界
|
次に流体潤滑の場合のすべり軸受の限界条件についてみてみます。 流体潤滑下では軸と軸受とは接触しません。そのため、理論的には、すべり軸受は静荷重下では半永久的に使用する事が可能です。3)しかしながら、現実には限界の主要因であるP、Vの他、図24)中の番号で示す要因(例えば、表面粗さ3)、潤滑油不足5))が大きくその限界を左右します。以下にその例を2,3あげることとします。 |
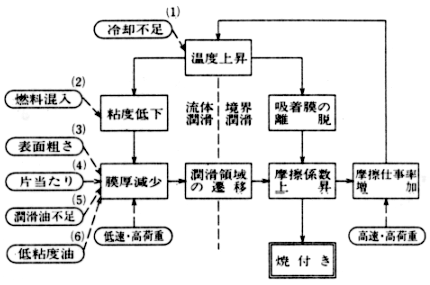
図2 焼付きの発生に至る過程
|
●最小油膜厚さと表面粗さ 図35)にガソリンエンジン用のコンロッド大端部軸受の最小油膜厚さ(hmin)が年と共にどのように変化しているかを示しました。ここに示す値はあくまで計算値でありますが、年々その値は小さくなり0.4μmをきるものも出てきています。近年、機械加工精度が全体的にあがり軸、軸受双方とも表面粗さ(R)の向上が見られますが、それでもhminとはほぼ同程度の値であり境界潤滑の入り込む余地が十分あり、その時には温度上昇を伴って焼付く場合もあります。 |
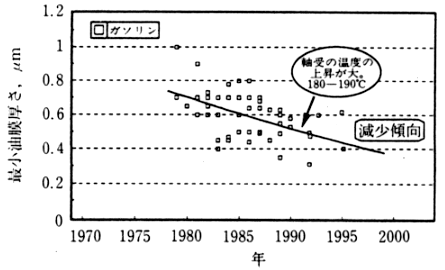
図3 コンロッド軸受の最小油膜厚さの変化
|
●潤滑油不足 図46)に潤滑油量と軸受背面温度との関係を示しました。図より軸受を流れる油量が10cm3/s以下になると軸受の温度は上昇を始め2cm3/s付近で焼付きに至る事が解ります。 |
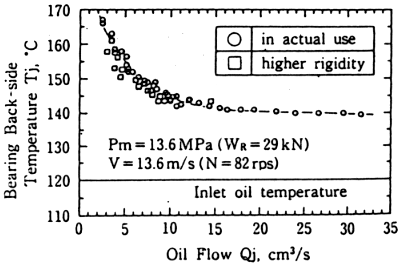
図4 軸受背面温度(Tj)と油量(Qj)との関係
|
現実の対応から限界がどこまで上げられるか、その結果、現在、限界はどこかについて述べます。 考え方は、図57)に示すストライベック曲線の 1)C点をいかに0に近づけるか(流体潤滑領域をいかに広げるか) 2)B点(混合〜境界潤滑領域)にある状態をいかに速やかにC点にもっていくかによって、その限界を大きく上げることが可能である。具体的には図2からわかるように十分な潤滑油で冷却、潤滑を行ない、軸、ハウジング、軸受の精度を極限まで向上させることです。しかし、現実にはコストを考慮にいれた生産技術では、ある程度のところでの妥協はやむを得なく、限界が決まっているのが実状です。 |
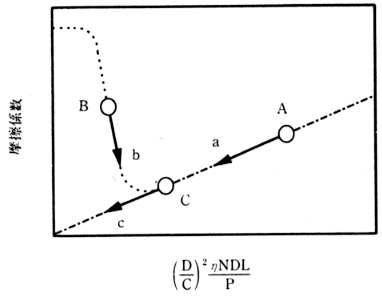
図5 ストライペック曲線
|
軸受側からの対応については、材料開発、最適設計、精度向上を行ない、他にも、軸受材の構造から片当たりによる集中荷重を軽減するための工夫もされています。図67)に軸受の構造を示します。いずれも1mm厚以上の鉄の裏金の上に十分な軸受特性を備えた軸受合金をのせた構造をもちますが、軸受合金の上(c)、または裏金との間(b)になじみをとる為のやわらかい層をもったものが多いです。なお、なじみ層は裏金の背面に付ける場合も考えられます。また、軸受合金の表層は必ずしも平坦ではなく、なじみの役割の他油膜保持の為の形状も考えられています。 その結果、図1に示すように面圧では約60MPa、すべり速度では約20m/s、hminでは0.4μmがほぼ限界となっています。この時、軸受の温度は160〜200℃となり、その限界は軸受材質により異なります。但し、レース用エンジンのように上記のような条件が整えば、60MPa×40m/sも可能となります。 |
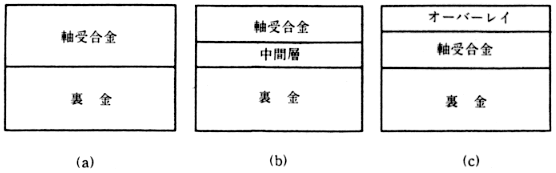
図6 軸受材の構造
|
「参考文献」 | |
|
1) |
渡辺真太郎他:日本潤滑学会東北大会予稿集、(1982)341 |
|
2) |
大豊工業(株)技術管理部:月刊トライボロジ、No.62(1992)78 |
|
3) |
曽田範宗:軸受、(1964)5 |
|
4) |
木村好次・河合望他:塑性加工におけるトライボロジ、(1988)36 |
|
5) |
大豊工業(株)社内資料 |
|
6) |
K.HASHIZUME & Y.KUMADA:SAE-Paper 910160.(1991) |
|
7) |
熊田喜生・福岡辰彦:日本潤滑学会トライボロジー会議予稿集、 (1992−5)441 (大豊工業技術管理部) |
|
「出典」 すべり軸受Q&A 月刊トライボロジ1993.3 p33,1993.4 p33 | |
Copyright 1999-2003 Japan Lubricating Oil Society. All Rights Reserved.